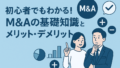こちらもあわせて読みたい
事業承継の現状と課題~なぜ今、準備が必要なのか
日本の中小企業の多くは、高度経済成長期に創業者が立ち上げ、現在は事業承継の時期を迎えています。中小企業庁の調査によると、中小企業経営者の平均年齢は約66歳に達し、70歳を超える経営者も増加の一途をたどっています。しかし、その半数以上が後継者未定という厳しい現実があります。
事業承継は単なる経営権の移転ではなく、長年築き上げてきた企業価値や従業員の雇用、取引先との関係、地域経済への貢献など、多くの要素を次世代に引き継ぐ重要なプロセスです。しかし、準備不足や計画性の欠如により、多くの企業が事業承継の過程で様々な問題に直面しています。
事業承継の失敗事例から学ぶ
事業承継の失敗事例は数多く存在します。ある老舗の製造業では、創業者が突然の病で倒れた後、明確な後継者が決まっていなかったため、経営の混乱が生じ、最終的に廃業に追い込まれました。また別のケースでは、後継者は決まっていたものの、経営ノウハウの引継ぎが不十分だったため、主要取引先を失い、業績が大幅に悪化したという例もあります。
これらの失敗事例に共通するのは「準備不足」です。事業承継は経営者の引退とともに突然始まるものではなく、5年、10年という長期的な視点で計画的に進めるべきプロセスなのです。
早期準備のメリット
事業承継の準備を早期に始めることには、多くのメリットがあります。
1. 選択肢の幅が広がる
時間的余裕があれば、親族内承継、従業員承継、M&Aなど、様々な選択肢を検討できます。また、最適な後継者を見極め、育成する時間も確保できます。
2. 税務対策が可能になる
相続税や贈与税の負担を軽減するための対策には、一定の期間が必要です。早めに準備することで、税制優遇措置を最大限に活用できます。
3. 円滑な引継ぎが実現する
経営ノウハウや取引先との関係性など、形式知化しにくい要素を後継者に伝えるには時間がかかります。十分な引継ぎ期間を設けることで、事業の継続性を確保できます。
4. 企業価値の向上が図れる
承継を見据えて経営改善や財務体質の強化を行うことで、企業価値を高めた状態で引き継ぐことができます。
事業承継の種類と特徴~自社に合った方法を選ぶ
事業承継には大きく分けて「親族内承継」「従業員承継」「M&A(第三者承継)」の3つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、自社の状況に最も適した方法を選ぶことが重要です。
親族内承継のメリット・デメリット
メリット:
– 会社の理念や文化を維持しやすい
– 取引先や従業員からの信頼を得やすい
– 経営権と財産(株式)の分散を防ぎやすい
– 早期から後継者教育を始められる
デメリット:
– 適切な能力を持つ親族がいるとは限らない
– 相続税・贈与税の負担が発生する
– 他の相続人との間で争いが生じる可能性がある
– 親子間の考え方の違いによる軋轢が生じることがある
従業員承継のメリット・デメリット
メリット:
– 会社の事業内容や文化を理解している人材に承継できる
– 従業員のモチベーション向上につながる
– 取引先や他の従業員からの信頼を得やすい
– 経営の連続性を保ちやすい
デメリット:
– 株式取得資金の調達が課題となる
– 経営者としての資質が必ずしも備わっているとは限らない
– 親族との利害調整が必要になることがある
– 経営責任の重さに耐えられない可能性がある
M&A(第三者承継)のメリット・デメリット
メリット:
– 株式の売却代金を経営者の退職金として確保できる
– 相乗効果による事業の発展が期待できる
– 従業員の雇用維持が期待できる
– 客観的な企業評価に基づく取引が可能
デメリット:
– 社風や経営方針が大きく変わる可能性がある
– 従業員の不安や反発が生じることがある
– 相手探しや交渉に時間と費用がかかる
– 情報漏洩のリスクがある
事業承継の準備タイムライン~5年、10年の計画で進める
事業承継は一朝一夕に完了するものではなく、長期的な視点で計画的に進める必要があります。理想的には5~10年前から準備を始め、段階的に進めていくことをお勧めします。以下に、時期別の準備事項をご紹介します。
5~10年前から始めるべきこと
1. 事業承継の方針決定
まずは、親族内承継、従業員承継、M&Aのいずれを目指すのかという大きな方針を決定します。この段階では、家族会議を開いて家族の意向を確認したり、信頼できる顧問に相談したりすることが重要です。
2. 後継者候補の選定と育成計画の策定
後継者候補を選定し、どのように育成していくかの計画を立てます。親族内承継の場合は、子どもが自社に入社する前から、将来の経営者としての教育を意識することも大切です。
3. 自社株式・資産の現状把握
自社の株式構成や事業用資産、個人資産などの現状を把握します。特に株式が分散している場合は、集約するための計画を立てる必要があります。
4. 会社の「見える化」
経営状況、業務プロセス、取引関係など、会社の様々な側面を「見える化」します。属人的な業務や暗黙知を形式知化することで、スムーズな引継ぎが可能になります。
3~5年前から始めるべきこと
1. 後継者の本格的な育成
後継者に実際の経営に関わらせ、徐々に責任ある立場を任せていきます。重要な取引先への紹介や、経営会議への参加など、段階的に経営者としての経験を積ませることが重要です。
2. 経営体制の整備
取締役会や経営会議など、組織的な意思決定の仕組みを整備します。ワンマン経営から組織的経営への転換を図ることで、経営者交代後も安定した経営が可能になります。
3. 財務体質の強化
借入金の返済や不採算事業の整理など、財務体質の強化を図ります。特に個人保証や担保に関する問題は、早めに対処することが重要です。
4. 株式・資産の移転計画の実行
相続税・贈与税の負担を考慮しながら、計画的に株式や資産の移転を進めます。事業承継税制などの優遇措置を活用することも検討します。
1~3年前から始めるべきこと
1. 具体的な承継時期の決定
具体的にいつ代表権を移譲するか、いつ会長職に退くかなど、具体的なスケジュールを決定します。
2. 関係者への説明
従業員、取引先、金融機関など、主要な関係者に事業承継の計画を説明します。特に金融機関には早めに相談し、理解と協力を得ることが重要です。
3. 事業承継計画書の作成
これまでの準備内容や今後のスケジュールをまとめた事業承継計画書を作成します。この計画書は、関係者との共通認識を形成するためにも役立ちます。
4. 権限の段階的委譲
日常的な業務判断から重要な経営判断まで、段階的に権限を委譲していきます。この過程で後継者の成長を見守りながら、必要に応じてサポートすることが大切です。
承継直前~承継後にすべきこと
1. 法的手続きの実施
代表取締役の変更登記や株式譲渡の手続きなど、必要な法的手続きを行います。
2. 挨拶回り
新旧経営者で主要取引先への挨拶回りを行い、円滑な関係の継続を図ります。
3. 経営理念・ビジョンの再確認
後継者を中心に、経営理念やビジョンを再確認し、必要に応じて刷新します。これにより、新体制での求心力を高めることができます。
4. 前経営者の役割明確化
前経営者が会長などの立場で残る場合は、その役割を明確にします。過度な干渉は避けつつ、必要なサポートを提供する関係性を構築することが重要です。
事業承継における税金対策~知っておくべき制度と活用法
事業承継において、税金対策は非常に重要な課題です。特に自社株式の評価額が高い場合、相続税や贈与税の負担が大きくなり、事業継続の障害となることがあります。ここでは、事業承継に関連する主な税制と、その活用方法について解説します。
事業承継税制の概要と活用方法
事業承継税制は、中小企業の事業承継を支援するための税制優遇措置です。2018年に大幅に拡充され、2027年3月31日までの特例措置として、より使いやすい制度となっています。
特例事業承継税制のポイント:
– 贈与税・相続税の納税猶予割合が100%(一般制度は80%)
– 対象株式数の上限撤廃(一般制度は総株式数の3分の2まで)
– 雇用維持要件の実質的な撤廃(一般制度では5年間で平均8割以上の雇用維持が必要)
– 複数の後継者への承継も対象(最大3人まで)
この制度を活用するには、事前に「特例承継計画」を都道府県に提出し、認定を受ける必要があります。計画の提出期限は2023年3月31日までとなっていましたが、現在は2027年3月31日まで延長されています。
種類株式の活用:
種類株式を活用することで、議決権と配当受取権を分離し、経営権と財産権を別々に承継することが可能になります。例えば、後継者には議決権のある普通株式を、他の相続人には無議決権だが配当優先の種類株式を承継させるといった方法が考えられます。
持株会社(ホールディングカンパニー)の活用:
持株会社を設立し、事業会社の株式を持株会社に移すことで、個人の相続税対策になるとともに、グループ経営の効率化も図れます。ただし、設立には一定のコストがかかるため、メリット・デメリットを十分に検討する必要があります。
生命保険の活用:
経営者が生命保険に加入し、相続人を受取人とすることで、相続税の納税資金を確保できます。また、法人が契約者・受取人となる「逓増定期保険」などを活用することで、企業の内部留保を増やし、自社株評価の引き下げにつなげることも可能です。
自社株評価の適正化
自社株式の評価額を適正化することで、相続税・贈与税の負担を軽減できる場合があります。例えば、純資産価額方式で評価される会社の場合、遊休資産の処分や負債の圧縮などにより、株式評価額を下げることが可能です。ただし、恣意的な評価減は税務調査の対象となる可能性があるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。
後継者の選定と育成~成功する事業承継の核心
事業承継の成否を大きく左右するのが、後継者の選定と育成です。適切な後継者を見極め、計画的に育成することが、事業の持続的発展につながります。
後継者の選定と育成~成功する事業承継の核心
後継者に求められる資質は、業種や企業規模、経営環境によって異なりますが、一般的には以下のような要素が重要とされています。
1. リーダーシップと決断力
経営者として組織をまとめ、重要な意思決定を行うためのリーダーシップと決断力は必須です。
2. コミュニケーション能力
従業員、取引先、金融機関など、様々なステークホルダーと良好な関係を構築・維持するためのコミュニケーション能力が求められます。
3. 変化への適応力と革新性
変化の激しい経営環境の中で、柔軟に対応し、必要に応じて革新を起こす力が重要です。
4. 財務・法務の基礎知識
経営判断の基盤となる財務・法務の基礎知識は、経営者として不可欠です。
5. 業界知識と専門性
自社の事業領域に関する知識や専門性も、信頼される経営者になるために重要です。
親族内後継者の育成ステップ
親族内承継の場合、後継者育成は長期的な視点で計画的に進めることが重要です。
1. 早期からの教育(学生時代~)
経営者の子どもとして、家庭内で企業経営や事業に関する話題に触れる機会を作ります。また、経済や経営に関する基礎的な教育を受けさせることも有効です。
2. 社外経験の奨励(大学卒業後~)
いきなり自社に入社させるのではなく、他社での勤務経験を積ませることで、客観的な視点や多様な経験を得ることができます。
3. 自社内での段階的な経験(入社後)
自社に入社後は、現場から管理職、役員と段階的にキャリアを積ませます。できるだけ多くの部門を経験させることで、会社全体を俯瞰できる視点を養います。
4. 経営参画(役員就任後)
役員に就任後は、実際の経営判断に参画させ、徐々に責任ある立場を任せていきます。この段階では、現経営者がメンターとして支援することが重要です。
5. 権限委譲(承継直前)
承継直前の段階では、大部分の権限を委譲し、現経営者はアドバイザー的な立場に徹することで、後継者の自立を促します。
親族外後継者(従業員等)の選定と育成
従業員や外部人材を後継者とする場合も、計画的な選定と育成が重要です。
1. 候補者の選定基準の明確化
どのような人材を後継者とするか、選定基準を明確にします。経営能力だけでなく、企業理念への共感度や人間性も重要な要素です。
2. 複数候補者の並行育成
複数の候補者を並行して育成し、その過程で最適な人材を見極めることも有効です。
3. 経営者としての教育
管理職としての能力と経営者としての能力は異なります。経営塾や後継者育成プログラムなどを活用し、経営者としての視点や知識を身につけさせることが重要です。
4. 株式取得のサポート
従業員が後継者となる場合、株式取得資金の調達が大きな課題となります。経営者持株会の活用や金融機関の融資斡旋など、資金面でのサポートを検討する必要があります。
5. 周囲の理解と支援の確保
親族外承継の場合、特に他の従業員や取引先の理解と支援を得ることが重要です。現経営者が積極的に後継者を支持する姿勢を示すことで、円滑な承継が可能になります。
事業承継時の課題と解決策~よくある問題への対処法
事業承継の過程では、様々な課題や問題が生じることがあります。ここでは、よくある課題とその解決策について解説します。
株式の分散問題への対処
創業者の相続などにより株式が分散してしまうと、経営の意思決定が難しくなることがあります。
解決策:
– 生前贈与や遺言による計画的な株式承継
– 株式買取資金の準備(生命保険の活用など)
– 種類株式の活用による議決権の集中
– 株主間協定の締結による安定株主工作
後継者を巡る親族間の対立
後継者の選定や資産分配を巡って、親族間で対立が生じることがあります。
解決策:
– 早期からの家族会議の開催と情報共有
– 公平な資産分配計画の策定(事業用資産と個人資産の切り分け)
– 第三者の専門家を交えた話し合い
– 明確な遺言書の作成
個人保証・担保の問題
経営者の個人保証や個人所有不動産の担保提供が、承継の障害となることがあります。
解決策:
– 「経営者保証に関するガイドライン」の活用
– 計画的な借入金の返済と財務体質の強化
– 事業用資産の法人への移転
– 金融機関との早期相談と関係強化
従業員・取引先の不安への対応
経営者交代に伴い、従業員や取引先が不安を感じ、離職や取引縮小につながることがあります。
解決策:
– 早期からの情報開示と丁寧な説明
– 新旧経営者による共同での挨拶回り
– 経営理念・事業方針の継続性の強調
– 従業員参加型の新体制構築
旧経営者の引き際と関与度合い
旧経営者が引退後も過度に経営に関与し続けると、新経営者の自立が阻害されることがあります。
解決策:
– 旧経営者の役割の明確化(顧問・相談役など)
– 段階的な権限委譲と引き際の設定
– 旧経営者の新たな活動領域の創出(社会貢献活動など)
– 定期的な対話による信頼関係の維持
専門家の活用~事業承継を成功に導くサポート体制
事業承継は専門的な知識と経験が必要なプロセスです。適切な専門家のサポートを受けることで、スムーズな承継が可能になります。
事業承継で活用すべき専門家とその役割
1. 税理士
相続税・贈与税対策、事業承継税制の活用、株式評価など、税務面でのアドバイスを提供します。
2. 弁護士
株式譲渡契約の作成、種類株式の設計、株主間協定の作成など、法務面でのサポートを行います。
3. 公認会計士
財務デューデリジェンス、企業価値評価、財務改善計画の策定などを支援します。
4. 中小企業診断士
事業承継計画の策定、後継者育成、経営改善など、経営面での総合的なアドバイスを提供します。
5. 金融機関
資金調達、M&Aマッチング、事業承継支援融資などの金融面でのサポートを行います。
6. M&A仲介会社・アドバイザリー会社
M&Aによる事業承継を検討する場合、相手探しから交渉、契約までをサポートします。
専門家チームの組成と活用方法
事業承継では、複数の専門家による連携したサポートが効果的です。
1. 中心となる専門家の選定
まずは、自社の状況をよく理解し、信頼できる専門家(多くの場合、顧問税理士や顧問弁護士)を中心に据えます。
2. 必要に応じた専門家チームの組成
中心となる専門家を通じて、必要に応じて他の専門家を紹介してもらい、チームを組成します。
3. 定期的なミーティングの開催
専門家チームと定期的にミーティングを開催し、進捗状況の確認や課題の共有を行います。
4. 役割分担の明確化
各専門家の役割と責任を明確にし、効率的なサポート体制を構築します。
公的支援制度の活用
事業承継を支援するための公的制度も積極的に活用しましょう。
1. 事業承継ネットワーク
各都道府県に設置された事業承継ネットワークでは、事業承継診断や専門家の紹介などを無料で受けられます。
2. 事業承継・引継ぎ支援センター
全国の主要都市に設置された支援センターでは、事業承継計画の策定支援やM&Aマッチングなどのサービスを提供しています。
3. 事業承継補助金
後継者が新たな取り組みを行う際に活用できる補助金制度です。設備投資や販路開拓などの費用の一部が補助されます。
4. 事業承継特別保証制度
事業承継時に必要な資金を調達する際に、信用保証協会の保証を受けられる制度です。
事業承継後の経営革新~次世代への飛躍のために
事業承継は単なるバトンタッチではなく、企業の持続的発展のための重要な機会です。承継後に新たな成長戦略を展開することで、企業価値を更に高めることができます。
承継後の100日計画
事業承継後の最初の100日間は、新経営体制の基盤を固める重要な期間です。この期間に以下のような取り組みを行うことをお勧めします。
1. ステークホルダーとの関係構築
従業員、取引先、金融機関など、主要なステークホルダーとの関係構築に注力します。特に重要な取引先には直接訪問し、新体制への理解と支援を求めます。
2. 経営理念・ビジョンの再確認と共有
企業の存在意義や目指す方向性を再確認し、全社で共有します。必要に応じて、時代に合わせた表現や内容に刷新することも検討します。
3. 現状分析と課題の洗い出し
財務状況、事業ポートフォリオ、組織体制など、様々な角度から現状を分析し、課題を洗い出します。
4. 短期的な改善策の実行
すぐに着手できる改善策を実行し、早期に成果を出すことで、新体制への信頼を高めます。
デジタル化・IT活用による業務効率化
多くの中小企業では、デジタル化やIT活用が遅れています。事業承継を機に、以下のような取り組みを進めることで、業務効率化と競争力強化を図ることができます。
1. 基幹業務のシステム化
販売管理、在庫管理、会計など、基幹業務のシステム化を進め、業務効率の向上とリアルタイムな経営情報の把握を実現します。
2. クラウドサービスの活用
初期投資を抑えながら、最新のITツールを活用できるクラウドサービスの導入を検討します。
3. テレワーク環境の整備
コロナ禍を経て、テレワークは新たな働き方として定着しつつあります。柔軟な働き方を可能にする環境整備を進めることで、人材確保にもつながります。
4. デジタルマーケティングの強化
自社ウェブサイトの刷新やSNS活用、オンライン商談の導入など、デジタルを活用した販路拡大を図ります。
新規事業開発と多角化戦略
事業承継を機に、新たな成長の柱となる事業の開発や多角化を検討することも重要です。
1. 既存事業の延長線上での展開
既存の技術やノウハウを活かした関連分野への展開は、比較的リスクの低い成長戦略です。
2. 異業種との協業・提携
異業種企業との協業や提携により、新たな価値創造を目指します。
3. 海外展開の検討
国内市場が縮小する中、海外市場への展開を検討することも一つの選択肢です。
4. M&Aによる成長加速
自社の成長戦略に合致する企業のM&Aを検討し、成長を加速させることも考えられます。
組織体制の見直しと人材育成
事業承継後の持続的成長のためには、組織体制の見直しと人材育成が不可欠です。
1. 権限委譲と意思決定プロセスの明確化
ワンマン経営から組織的経営への転換を図り、権限委譲と意思決定プロセスの明確化を進めます。
2. 次世代リーダーの育成
将来の経営幹部となる人材の発掘と育成に注力します。外部研修の活用や、重要プロジェクトへの参画機会の提供などが有効です。
3. 多様な人材の活用
女性、シニア、外国人など、多様な人材の活用を進めることで、新たな視点や発想を取り入れます。
4. 評価・報酬制度の見直し
成果や貢献度を適正に評価し、モチベーション向上につながる評価・報酬制度を構築します。
まとめ:今日から始める事業承継準備
事業承継は、経営者にとって避けて通れない重要な経営課題です。「まだ先のこと」と先送りにせず、今日から準備を始めることが、成功への第一歩です。
事業承継準備の第一歩
1. 現状の棚卸し
自社の経営状況、株式構成、資産状況などを整理し、現状を把握します。
2. 承継の方向性の検討
親族内承継、従業員承継、M&Aなど、どの方向性を目指すのかを検討します。
3. 専門家への相談
顧問税理士や顧問弁護士など、信頼できる専門家に相談し、アドバイスを受けます。
4. 家族との対話
家族と事業承継について率直に話し合い、互いの意向を確認します。
事業承継計画書の作成
これらの検討を踏まえて、事業承継計画書を作成します。計画書には以下の内容を盛り込みます。
– 現状分析(経営状況、株式構成、資産状況など)
– 事業承継の方針(誰に、いつ、どのように承継するか)
– 具体的なアクションプラン(時期別の実施事項)
– 想定されるリスクと対策
計画書は一度作成して終わりではなく、定期的に見直し、状況の変化に応じて更新していくことが重要です。
無料でできるM&A査定サービスの活用
事業承継の選択肢の一つとしてM&Aを検討する場合、まずは自社の価値を客観的に把握することが重要です。「MA AI査定」では、成約データ3,000件から学習したAIを活用した無料の企業価値査定サービスを提供しています。
簡単な質問に答えるだけで、自社の概算価値を無料で算出できるため、M&Aを検討する際の第一歩として最適です。また、M&Aに関する様々な情報や専門家のサポートも受けられます。
事業承継は経営者にとって一生に一度の大きな決断です。十分な準備と適切なサポートを受けながら、次の世代に向けて最良の選択をしましょう。
無料・匿名でOK!!チェックで営業電話なし!!3分で自社の売却金額をAIが算出!!
M&Aの基礎から学べる、お金と経営の“出口戦略”マガジン